The Long Way to a Simple House
お久しぶりです、佐藤です。
しばらくブログが空いてしまいましたが、また少しずつ書いていこうと思います。今日は、家のかたちについて、少し考えてみたことをお伝えしたいと思います。
長くものをつくっていると、形がだんだん単純になっていくことに気づきます。
最初は、そうじゃなかった。高さを変えたり、部品をつけたり、囲ってみたり、飛び出させてみたり。にぎやかに、あれこれ手を加えては「これでいいのか?」と自分に問いかけていました。
それでも、そういう時期につくった建築には、ある種の勢いがありました。
理屈よりも、楽しさが前に出ていた気がします。もちろん、理屈がなかったわけではありません。でも、当時はそれを超える何かがあった。今思えば、あれはあれで、必要な遠まわりだったのだと思います。
年齢を重ねていくうちに、自分の中に何かしらの「かたちの感覚」ができてきます。
それはルールのようでいて、そうではない。守らなければいけないものではないけれど、自然と従ってしまうような感覚です。
たとえば、「なるべく少ない線で表現できるほうがいい」と思うようになりました。
限られた線で表現できることが増えてきて、そこに自由を感じるようになります。
誰かに「いやいや、まだ無駄が多いよ」と言われれば、それはそれで仕方ないのですが、それでもシンプルな方向へと向かう傾向は、なんとなく実感としてあります。
もちろん、単純なものが良くて、複雑なものが悪いというわけではありません。
それぞれに良さがあって、その時々にしか出せないかたちというのが、確かにあるように思います。
だから、いま大事にしているのは、「正直であること」です。
派手さを追わなくなった今でも、何か新しいことをやりたいと思う気持ちはあります。
でも、それはもう、昔のようなやり方ではなく、もっと静かな方法でできる気がします。
シンプルな家をつくるのには、案外時間がかかるものなのかもしれません。
いろんな道を通って、ようやく戻ってくる場所。そんな感じがしています。
佐藤隆幸
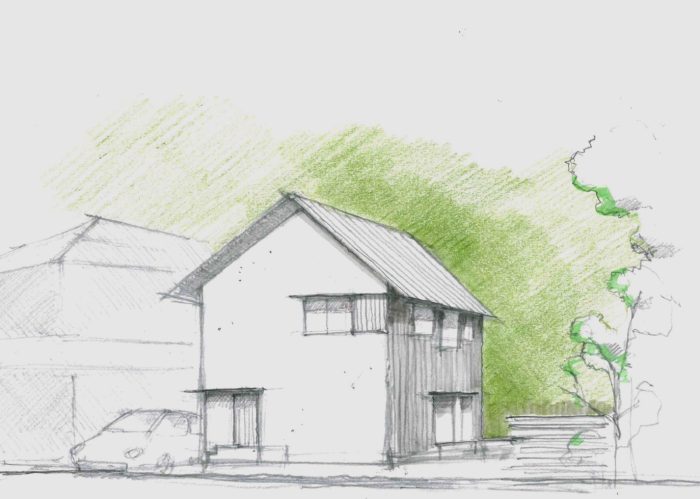
佐藤隆幸
最新記事 by 佐藤隆幸 (全て見る)
- 皆様、良いお年を - 2025年12月22日
- 堀部安嗣さんの自邸 - 2025年11月22日
- シンプルな家ができるまでの、遠まわりな話 - 2025年5月4日
